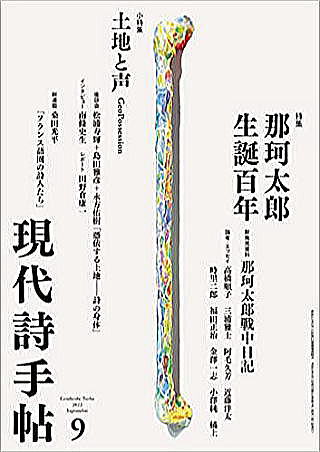太宰治と新発見の「那珂太郎 戦中日記」をめぐって
=太宰治を訪ねた出陣学徒たち:堤重久・三田循司・・=
・・はじめに・・
昨年(令和4年(2022))、那珂太郎の戦中の日記の一部が発見され、その全文が
「現代詩手帖」(思潮社)の「9月号」(2022)と「10月号」に分載された。
日記は、 最初のページに「2603年」「ノオト(第十一冊目)」と書かれ、
繰り上げ卒業の月である「昭和18年(1943)9月1日から同18日付まで」で、
これは、志願した海軍予備学生の合否通知を待つ期間でもあった。
「現代詩手帖-9月号」は、「那珂太郎 生誕百年」を特集し、この新発見の日記とともに
関係者の論考、エッセイを掲載しており、これらにより入隊直前の那珂の心情、行動、
この日記で初めて明らかになった二度の太宰治訪問の様子など、日記本体が発する
那珂本人や太宰治、友人たちの当時そのまま、生の姿がより鮮明に伝わる。
日記を発見した小澤純は、日記に載る人物名などには略歴、概要などの注釈を付し、
論考「那珂太郎と太宰治の1943年9月」(同誌9月号)で、発見の経緯や那珂と太宰
との関係、周辺状況など興味深い解説、考察を行っている。 (本項文中 敬称略)
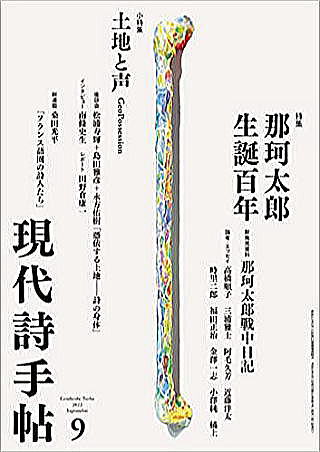
「現代詩手帖」9月号(2022)表紙
(表紙デザイン 戸塚泰雄
・表紙作品 加藤巧)
|
ー特集 那珂太郎 生誕百年ー
・新発見資料 「那珂太郎 戦中日記」
・論考・エッセイ(執筆者 表題)
三浦雅士 思想が詩に結晶するということ
阿毛久芳 煩悶する末期の眼からの声
小澤純 那珂太郎と太宰治の1943年9月
福田正治 父・那珂太郎
高橋順子 「まぼろし」という物
近藤洋太 那珂太郎と真鍋呉夫
時里二郎 「もう残りの時はわづかしかない」
金澤一志 ほととぎ朱の音楽
橘上 語りえぬものに対して沈黙しない
|
この当時(S18=1943)、日本軍はガダルカナル撤退開始(2月)、山本連合艦隊司令
長官戦死(4月)、アッツ島守備隊全滅(5月)など、戦況は日に日に悪化していた。
兵員補充、増強のため、大学の繰り上げ卒業、さらには徴兵猶予停止(S18/10)など
で多くの学徒が入隊、戦地に赴く状況だった。(繰り上げ卒業は、昭和16年から実施)
繰り上げ卒業すると、ほとんど直ぐに召集だった。
この時期、那珂の他にも入隊の前に太宰を訪ねた文学青年は多く、(堤重久、戸石泰一、
三田循司、桂英澄ら)、それぞれに「これが最後になるかもしれない・・」の思いがあった。
本項は、そうした戦死を覚悟した学徒らと太宰との交流、作品との関連などを記す。
-------------------------------
・・「那珂太郎」の ご紹介・・
那珂 太郎(なか たろう:本名 福田正次郎) T11(1922)~H26(2014):享年92歳
詩人(「歴程」同人):日本芸術院会員(H6・1994)
大正11年(1922)1月23日、福岡市生まれ。旧制福岡中学校を経て、旧制福岡
高等学校を卒業(S16=1941)。高校では同人誌に作品を掲載するなど文学を
志向し、伊達得夫(戦後、書肆ユリイカを創設)ら文学仲間との交友を深めた。
東京帝国大学文学部国文科入学(S16/4)。この年12月8日、太平洋戦争開戦。
同校を繰り上げ卒業(S18/9)、土浦海軍航空隊(海軍予備学生)入隊(S18/10)。
海軍兵学校国語科教官(S18=1943/12)。広島県江田島、長崎県針尾、山口県防府
と任地が変わり終戦(S20=1945/8)。福岡へ復員(S20/9)、直ぐ上京(S20/10)。
上京後は、教員として都立高校などに勤務。詩作を続け第一詩集となる
「ETUDES」(S25=1950:書肆ユリイカ)を刊行、「歴程」同人(S26)となる。
日本語の特性を音楽性で捉えた詩集「音楽」(S40=1965)で室生犀星詩人賞、
読売文学賞を受賞するなど、多くの賞を受賞。日本芸術院会員(H6=1994)。
東京都杉並区久我山に新居(S36=1961)を建て、荻窪の古い家から引っ越した。
後に、久我山を捩って「空我山房」と称し、終の棲家とした。
平成26年(2014)6月1日逝去(享年92歳)。
(本項末に「那珂太郎 略年譜」掲載。参照ください)
Ⅰ.[那珂太郎 戦中日記」と太宰治
(筆名「那珂太郎」を使用前のことについても「那珂」名で記した。)
1.先輩矢山哲治が「太宰治を読め!」
(1)那珂の少年時代
・那珂の随筆「遠い記憶」に次の一節がある。
「世界は理由もなく目あてもなく、ただ在る。さういふ世界の中の芥子粒のやうな存在で
ありながら、なぜものを感じたり思ったりして自分は生きてゐるのか。やがてはあの
彩られた雲と同じやうに、自分もまた確実に消滅してしまふ筈なのに、なぜいまここに
感じ且つ思ふものとして在りつづけるのか、理屈ではなく、紛れやうもない切ない感覚
として、存在すること自体に私は恐怖をおぼえた。」
・すでに、文学を志す感性、素地が見られる。
この後の那珂の詩作の源泉でもあろう。
ちなみに、戦中日記(9月1日(S18=1943))には、「俺のペシミズムと虚無感とは、
何処でどうなっても永遠に変る筈はない・・・」と記している。
(2)福岡高等学校(旧制)時代
①随筆「『こをろ』の頃Ⅰ」によると、旧制福岡高等学校に入学(S13=1938/4:16歳)した年に
校友会雑誌に”小説もどき”の短い作品を投稿したが、ボツになった。
その時、最上級生で文芸部委員の矢山哲治(*)に作品を厳しく評され、「太宰治を読め!」と
勧められた。
(*)矢山哲治(T7=1918~S18=1943):同人誌「こおろ」(S14)主宰。入隊(S17)するも結核で除隊。
療養中に列車に轢かれて死去。事故か自殺か不詳だが、自殺との見方が多い。
那珂はまだ太宰の名を知らなかったが、「晩年」、「虚構の彷徨、ダス・ゲマイネ」などを読み、
その後かなりの期間、太宰治という作家の文体に幻惑されることになった。
②クラス雑誌「青々」(*)(1号:S15=1940/1)に本名で短編小説「失題」を載せた。
作品の冒頭に、「こいつ太宰の真似をしていやがるな、なあんとおっしゃるかもしれない。」と
書き、さらに、太宰に切手を貼らない手紙を出したら「なっちゃいない返事がきた」と太宰を
実名で登場させるなど、太宰作品の強い影響が窺える。
(この手紙と返信のエピソードは、伊達得夫の随筆「幾歳月」によれば実話である。)
(*)「青々」(せいせい)は、創刊号(S15・1940)~第5号(終刊:S21・1946)の
福岡高等学校(旧制)文科乙類の謄写版印刷によるクラス雑誌。
昭和56年(1981)に、合本した復刻版が刊行され(第2号は未発見で収録なし)、
「旧制福岡高等学校文科乙類第十七回生」とある。
中村稔著「回想の伊達得夫」に、「福岡高校は青陵と称していたらしい。」、「この青陵
から「青々」と題名が選ばれたのではないか、と私は想像している。」とある。
(ネット情報によれば、同校同窓会は「青陵会」で、寮歌にも「青陵」の文言が入る。)
また、同著には、どの号にも奥付はなく、発行年月日は記載がないが、第3号には
住所録が載り、「昭和16年10月現在」とあるので、この秋の刊行と思うとある。
③那珂は、この2か月後の春休みの3月(S15=1940)に、初めて三鷹の太宰宅を訪問した。
2.太宰治と初対面(S15/3=1940)・・那珂太郎18歳、太宰治30歳
(1)40年後に回想して・・”心弱きダダ作家”
①大宰との初対面を、那珂は詩集「空我山房日乗其他」(1985)中の詩「池畔遠望」と随筆
「回想的散策」(1994)に記しているが、この二作品は初対面から40年余以上を経ての回想で、
この間には太平洋戦争、太宰の死、自身の詩人としての名声、など状況の激変がある。
②詩「池畔遠望」は、極月某日(注:昭和56(1981)年12月)、還暦を迎える那珂が井之頭公園を
散策中に池畔で卒然と太宰を想起しており、「回想的散策」はさらに10年後の作である。
大人の冷静な目で大宰を”心弱きダダ作家”と回想している。
・この回想によれば、初対面の時、太宰は「チェエホフを読め」と言ったという。
太宰は、ちょうど10年前(S5=1930)、東京帝大に入学(20歳)すると、井伏鱒二に強引に
面会を求めて初対面となり、太宰は原稿を持参して読んでもらった。この時、太宰は、
井伏に「私の真似などしないで、チェーホフなど古典を読みなさい・・」と言われている。
那珂は初対面時に作品、例えば太宰を真似たような「失題」(S15/1:「青々」)を持参したか
不明だが、何か微笑ましいエピソードである。
(2)「戦中日記」(S18.9.3)で・・”緊張した”
・今回発見の「戦中日記」の「9月3日」(S18・1943)に、「太宰さんは、3年半前-高等学校の時
来たときは、こはくて胸がどきどきして、息苦しいほどだったが、今日こんなにして逢ってみると
じつに親しい気がする。愉しかった。」とある。
・40年以上を経た後の回想と異なり、「戦中日記」は、3年半ぶりに本人を前にして甦った初対面、
18歳の高校生の実感、ナマの心情だろう。
=このころ(S15)の太宰治=
井伏鱒二の世話による再婚(S14/1)で得た平穏な家庭生活のもと、甲府から三鷹へ転居し
(S14/9)、懸命な執筆で新進として認められるようになり、妻美知子の「回想の太宰治-
旧稿」には、「15年春ごろには原稿依頼が増加して、著書も次々刊行され、昭和12、3年頃
とは一変した状況になっていた。」とある。
例えば、「女の決闘」は「月間文章」誌に連載中、「走れメロス」はこの3月の脱稿とされる。
井伏ら知己、友人との交遊も頻繁になり多忙な日常だが、若い文学青年の来訪も急増したに
違いない。那珂もそうした状況での訪問者だが、比較的早い時期だったろう。
ちなみに、後に太宰門下として名の残る小山清、田中英光、若手では戸石泰一、三田循司、
堤重久らの太宰との初対面はこの年(S15)の末頃からである。
・那珂はこの1年後(S16/4・19歳)に東京帝国大学文学部国文科に入学するが、繰り上げ卒業
(S18/9)となって10月1日に入隊(海軍予備学生)する。
3.入隊直前、3回の太宰訪問(S18(1943))
(1) 9月3日、「戦中日記」に”愉しい”
・この日に太宰を訪問した経緯や先客(注1)がいたこと、愉しかったこと、夕方、太宰と3人で
吉祥寺のスタンドに入ったこと、偶然、井伏鱒二が入ってきたこと、那珂持参の原稿(注2) は
7日には読むヒマがあるとのことで7日に再訪することにしたこと、などを記している。
・この日の太宰の言については、9月5日の日記に、伊達(注3)宛のハガキを載せている。
それによると、「太宰は、陛下を心からおしたひ申し上げ、そのためにこそ戦場に於いて
心から死ねるのだと云った。」と書き、これに関する自分の受け止め方、死と生についての
自分の思いを伊達に伝えている。
この時、那珂は海軍予備学生を志願しており、結果を待っていた。
10月1日入隊という決定の通知が届いたのは9月21日頃で、この間、これが最後になるかも
しれないという思いで友人らとの往来や死を身近に感じながら真剣に生を考える姿が綴られていく。
当時の文学部学生ならではの内容、文面とも思えるが、普通の日記というより、いつか、
何らかの形で他者の目に触れることを意識した書き方で、冷静な筆致が印象的である。
(注1)先客は、石沢深美(1918~未詳)。この時は慶應義塾大学文学部在籍。(後記Ⅱ.参照)
〈注2)持参した原稿は、自作品「ああああ」、「らららん」と「八 月のノオト」である。
「らららん」は、「青々」(三号:S16=1941)に掲載の小説で、第一詩集「ETUDES」(S25)
に改稿して収録。「ああああ」と「八月のノオト」は内容、所在など明らかでない。
(注3)伊達得夫(1920~1961)。 福岡高校で那珂と同級生。この時は京都帝国大学経済学部
在籍。生涯にわたる親密な友。(後記4参照)
(2) 9月7日、「戦中日記」に”強烈なショック”
・この日、予定通り再訪したが先客(画家)があり、一緒に吉祥寺のスタンドへ直行した。
太宰は、前回持参の原稿については要領を得ない返事をし、天皇への絶対帰依、滅私奉公
を言い、軽み‥正常歩で進め、兵隊はこの信仰がつかめないとみじめなことになると説いた。
ところが自分は‥”滅死彷徨だ。信仰が持てない” と、内にある迷いに思い悩む。
・9月8日も昨夜の太宰とのことを思い、打ちのめされて意気消沈と考え込み「鉄面皮」を読む。
・太宰の言動は、那珂にすれば自分の心的状態を拒否された、取りつく島もなかったという強烈
な印象だった。(9月18日の記述の * 以降・・後記4.参照)
・太宰は、この翌々日の9月9日、入隊前日の桂英澄に、「軍隊では人並みに、平凡に、という
ことを忘れないように」などと言った。(桂英澄著「入隊前夜」‥後記Ⅱ-1-(2)参照)
この違いは、会話の場所やメンバー、親交の深さにもよろうが、那珂の場合には、太宰が、
那珂の原稿や会話から感じ取った悲観的、虚無的気質、若さ(青さ)に軍隊生活への適合を
危ぶみ、迷いがあるなら先ず現実を受け入れよ、と諭したのではないだろうか。
「軽み」の意味は難しいが、苦悩は飲み込むこと、流れに沿った言動で対処すること・・、
平たく言えば結論は桂への言葉と同様になろうか。
・太宰宅を訪れていた三田循司(繰り上げ卒業で入隊)は、アッツ島玉砕(S18/5)兵士の一人
だったが、太宰が三田の死を知ったのは新聞に名前が載った8月29日かその直後である。
この時に受けた強い衝撃が関係している・・那珂の姿に三田を感じさせるものがあったかも
しれない。(後記Ⅱ-3.参照)
(3) 9月下旬、「回想的散策」に”太宰の昂り”
・今回発見の「戦中日記」は9月18日付までなので不明だが、「回想的散策」によれば、入隊
(10月1日)の数日前に、「もう二度と戻れるかどうかわからない、別れの挨拶に、といふ
悲壮感めいた気持もなかったわけではない。」ということで訪問した。
・この時も吉祥寺の屋台へ行ったが、太宰は店のあるじと来店客に、この人は明日戦地へ行く
と繰り返し紹介した。直ぐ戦地へ行くわけではないので恥しく辟易したが、太宰の昂ぶった
気持が推しはかられ感動したと振り返っている。
戦後の回想で、那珂は初対面と9月下旬の太宰訪問を記しているが、
3日と7日の2回の訪問について触れた文章は見当たらなかった。
長い時の経過と複雑な心境が窺えるということだろう。
4.山岸外史を訪ねて心安らぐ(S18/9)
この日記ノートは9月18日の日付が最後だが、18日の記述の次に * を入れて19日以降の
ことを記している。入隊日(10月1日)の直前に追記したのだろう。
①19日夜、京都に居る親友の伊達が訪ねてきた。何日間か共に親しく賑やかに過ごした。
②一夜、山岸外史を訪ねた。この時のことについて、太宰の場合には取りつく島もなかったが、
「ここでは、自分がそのまゝ許容されてありのまゝに自分を吐露することが出来る。目上の
人でこんな包容性を示してくれる人は他にいない。」などと山岸に感謝、惹かれている。
・ちなみに、三田循司(アッツ島で玉砕)の日記(S16.11.26付(*))および太宰の小説「散華」
から、三田も太宰を訪ねながら山岸に魅かれていることが分かる。
(*)「三田循司関連資料」(小澤純調査報告(2022/5)より・・詳細後記参照)
5.入隊(S18.10.1)決定は修学旅行の感覚
①伊達と自分の下宿へ帰ると海軍省から「10月1日、土浦海軍航空隊入隊」の通知がきていた。
「修学旅行へ行く日割りが決まった程度の感じ。しかもその修学旅行に、一向おれは気乗り
していないんだが。」と書いている。
②下宿の荷物の処置は煩わしい・・。
「これだから現実世界といふものはイヤなんだ。」
「まゝよ、荷物は誰かが片付けてくれるだろ。俺は拱手傍観だ。」
ここで、このノートの日記は終わる。
正確な日は不明だが、記述の前後の関係から、下宿に帰ったのは22日頃と察せられ、
入隊の通知はその前日くらいに届いていたのだろう。
入隊まで約1週間、その間に前記のように太宰を訪問、これが生涯最後の対面だった
だろう。
太宰には理解されなかったというショックを受け、山岸に救われる思いがした那珂が、
ここで再び太宰を訪問、魅かれる何かが太宰にはあったということだろう。
6.終戦(S20.8.15)-再出発
(1)作品の発表
①東大時代(S16/4~S18/9)
・那珂が東大時代に発表した作品で確認できるのは、福岡高校(旧制)のクラス雑誌
「青々-3号」(S16/10)に掲載の小説「らららん」と詩、俳句、「同-4号」(S17/9)に
掲載の俳句で、著者名は、いずれも「福田正」である。
・太宰訪問時(S18.9.3)に「らららん」を持参したが、発表作と同一かは分からない。
戦後刊行の第一詩集「ETUDES」(S25=1950)収録の「らららん」は改稿作である。
②海軍時代(S18/10~S20/8)
・那珂は海軍時代も作品を書いており、戦中と終戦後に発表している。
・「止里可比(4号)」(S19/9=1944)に詩「雪のふる夜は」、「阿呆鳥」が載っている。(注1)
発行は、江田島の海軍兵学校教官の時で、作者名は「那珂太郎」である。
「那珂太郎」名の使用は、この時が初めてだろう。(これ以前の使用は確認されていない。)
戦時中、立場もあり本名での発表を避けたのではないか。(注2)
(注1)「止里可比」は、福岡高校(旧制)出身の各務章、湯川達典、田中小実昌らが中心
になって発行したクラス回覧雑誌(S17~S21に7冊を発行)で、現存は2冊のみ。
誌名は、学校所在地「鳥飼=とりかい」に因む。
寄稿者の一人、田中小実昌の随筆「回覧雑誌「止里可比」のこと」(2016:「題名は
いらない」所収)に、「鳥飼の古語で、万葉集にもでているとかきいた。」とある。
(注2)筆名「那珂太郎」について
「那珂」は出身地福岡の「那珂川」からで、「太郎」は男性名の代表ということだろう。
友人の伊達得夫著「幾歳月」(「詩人たち-ユリイカ抄-」所収)に次の記述がある。
「ある日、ペンネームを考えた、と言った。そして、いくぶんテレくさそうに見せたのは
那珂太郎という、いかにもペンネームくさい名であった。(中略) 「詩学」や「歴程」の
誌上に那珂太郎の名が、折々見られるようになったのはそれから間もなくであった。」
冒頭の「ある日」は、文章の流れなどから「戦後」である。「詩学」(S22=1947発刊)や
「歴程」などに初めてこの名が載ったのは、おそらく戦後も数年を経てからだろう。
つまり福田正次郎が「那珂太郎」を筆名としたのは戦後であり、「止里可比(4号)」
に使用したのは本名を隠すためのその時限りの仮名に過ぎなかったといえよう。
③終戦(S20=1945 .8.15)
・海軍兵学校分校(山口県防府)国語科教官(海軍中尉)で終戦を迎え、復員で郷里の福岡市
へ帰り(S20/9)、直ぐに上京した(S20/10)。
・「青々(5号)」(終刊号:S21=1946/10)に、小説「婁見の手帖」が載っている。
作品の末尾に(一九四四年六月)とあり、教官として江田島に勤務した時期の執筆となる。
海軍予備学生時の日常体験を日記形式で記した小説で、那珂と思しき主人公は戦死する。
自分の戦死で締めたのは、戦場に送られた多くの同期生の戦死の報に心が痛み、偶然の
選別による運命とはいえ戦場に出ない立場からくる負目のような複雑な心情の反映だろう。
発表時、自分は過去にとらわれず、新たな道を進むという気持を込めたかもしれない。
著者名は「福田正次郎」の本名である。
・この小説「婁見の手帖」(S21)の後、那珂は、第一詩集「ETUDES」(S25)(*)に「らららん」
(「青々」(3号・S16)」掲載を改稿)を載せただけで、新たな小説は発表していない。
戦後は詩作に集中したといってよかろう。
(*)第一詩集「ETUDES」刊行のエピソード・・著者名は「福田正次郎」
昭和25(1950)年5月、那珂の初の詩集「ETUDES」が刊行された。
発行は「書肆ユリイカ (発行者・伊達得夫)」である。
「書肆ユリイカ」は那珂の福岡高校からの親しい友人である伊達得夫が
昭和23年に創設した出版社だが経営不振に陥っていた。伊達が那珂を
訪ねた折、廃業のつもりと告げると、那珂は「最後におれの詩集を作らんか。
おれの詩集は生徒が買ってくれるからな。売れるぜ」と言い、刊行を決めた。
(伊達得夫著「首吊り男」(「詩人たち-ユリイカ抄-」所収)より)
著者名は本名の「福田正次郎」である。
この時点で筆名「那珂太郎」を使っていたかはっきりしないが、教え子には
本名の「福田正次郎」でないと通用しない状況であったことは確かである。
この詩集は好評で完売したことなどがあり、「書肆ユリイカ」は存続できた。
伊達が発刊した(S31/10)詩誌「ユリイカ」は、伊達の死(S36)で途切れたが、
青土社が復刊し(S44)、現在も続く詩主体の貴重な文芸総合誌である。
(2)那珂と太宰・山岸
海軍入隊以降の那珂と太宰・山岸との交流についての資料は見当たらなかった。
次の状況から、直接会うことはなかったと察せられる。
・那珂は終戦直後に上京(S20/10)したが、当初は生きることで精一杯だったのではないか。
私立女学校の時間講師などをした後、翌年春(S21)、都立第十高等女学校(現豊島高校)
の教諭になり、以降、長期にわたり高校、大学で教鞭をとり、詩作も続けるが、戦後の混乱期
は学校の一室に男性教諭3人が衝立で仕切って生活する(S23)ような有様(*)だった。
(*)この頃のことに関して、那珂本人は随筆「径」(「那珂太郎詩集」(S44:思潮社)
で触れているが、教え子の一人である詩人吉原幸子は「師への手紙」(同上)
でユーモラスに活写している。
それぞれ、那珂の人物と文学を知るうえで興味深い一文である。
・太宰は戦中から戦後の作家活動で名を高めており、疎開から三鷹に戻って(S21/11)からは
超多忙の日が続き、複雑な女性関係も加わって、以前の交友関係は一変している。
・山岸は山形に疎開中で、太宰の死(S23/6)に際して何年か振りで上京した。
それぞれの実生活の状況から、そして那珂が詩作て独自の道を求める風があり、
この時期に、積極的に太宰を訪ねる気にはならなかったと察する。
(3)那珂-伊達、伊達-太宰
①那珂の生涯の友 伊達得夫(T9(1920)-S36(1961):享年40歳)
伊達得夫は「書肆ユリイカ」創設(S23)、詩誌「ユリイカ」創刊(S31)で知られるが、福岡高等
学校(旧制)で那珂太郎と同級生で当時から文学を通じて親交を深め生涯の友となった。
今回発見の那珂の日記には伊達が頻繁に登場する。特別なこの9月とはいえ、書簡だけでなく、
両者が居住する東京、京都間を行き来し、二人で山岸を訪ねるなど、親密ぶりが際立っている。
伊達は京都帝国大学経済学部に進学した(S16/4)。何故この進路だったかはっきりしないが、
大学では「京都帝国大学新聞」の編集員になり、同紙に論説や随筆、映画評論を寄稿している。
筆名に「伊達河太郎」も用いた。(「河太郎」は「ガタロウ」・・那珂宛電報(S18.9.10)発信者名)
(伊達の生涯に関しては、中村稔著「回想の伊達得夫」(2019/7:青土社)に詳しい。
伊達が自身の過酷な軍隊生活を書いた小説「風と雁と馬蓮花」も収録している。
この小説は「青々(5号-最終号)」に初出で、那珂の「婁見の手帖」とともに載っており、
偶然ではなく、二人による特別の意図が込められているように思える。)
②伊達と太宰の「待つ」・「津軽」
・太宰治著「待つ」の発表経緯
「京都帝国大学新聞」の編集に携わっていた伊達は、太平洋戦争開戦(S16/12)直後に、太宰
に同紙3月号に載せる原稿を依頼するため三鷹の太宰宅を訪ねた。
太宰は引き受けて、1月(S17)に「待つ」を脱稿、京大新聞へ送付した。
ところが、結果は時局不相応ということで不掲載となった。(*)
太宰は、この原稿のコピーを折から刊行作業が進んでいた「創作集 女性」に追加収録すべく、
2月半ば過ぎに発行所の博文館に送付した。(*)
「待つ」の初出は、この「創作集 女性」(S17/6:博文館)である。
(*)この経緯に関する妻美知子の記述や太宰の博文館宛「2/20付ハガキ」の紹介など、
「太宰治全集 第4巻-解題(山内祥史)」(1989/12:筑摩書房)に詳しい。
なお、この京大新聞不掲載に関し、伊達は「発禁の思い出」(「詩人たち-ユリイカ抄-」)に、
「新聞発行後に当局の検閲で発禁」とある。
該当号(第344号)は「待つ」を差し替えて再発行したのだろう。
(詳細は、追って作成する別項目「待つ」で触れる予定。)
・太宰治著「津軽」:戦後の最初の発行は伊達が装幀
伊達は見習士官になって岐阜で終戦を迎え京都に復員、すぐに上京し前田出版社に勤めた。
この前田出版社は太宰の「津軽」を戦後最初に再出版(S22/4)したが、装幀は「伊達河太郎」
(=得夫)である。
この「津軽」は挿絵を載せていないが、初版(S19:小山書店)には太宰が自筆の挿絵を載せて
おり、書肆ユリイカの出版物のカットを書くなど多才ぶりが窺える伊達との間でより濃厚な接触
があったと思うが、この直後に両者の人生は激動の時に入り、関係はここで終わったようだ。
(「那珂太郎 戦中日記」の項の主な参考図書)
・「現代詩手帖 9月号」(2022/9:思潮社)所収
・「那珂太郎戦中日記(上)」
・小澤純著「那珂太郎と太宰治の1943年9月」
・現代詩手帖10月号」(2022/10:思潮社)所収
・「那珂太郎戦中日記(下)」
・「那珂太郎―はかた随筆集」(2015:福岡文学館)所収
・「遠い記憶」(1976)
・「『こをろ』の頃Ⅰ」(1978)
・「回想的散策」(1994)
・「年譜」「初出一覧」 など。
・那珂太郎著「空我山房日乗其他」(1985:青土社)所収
・「池畔遠望」
・伊達得夫著「詩人たち―ユリイカ抄―」
(S56/10・第6刷:日本エディタースクール出版部)
・山内祥史著「太宰治の年譜」(2012:大修館書店)
Ⅱ.入隊を前に太宰治を訪ねた学徒たち
1.堤 重久のグループ
(1)堤 重久(T6(1917)~H11(1999)・・没年は、今回の「現代詩手帖」(2022/9)により確認
・堤は東京都生まれ。東京帝国大学文学部独文科在学中の昭和15年12月頃、太宰宅を訪問し
初対面した。以降、頻繁に訪問するなど、師弟として親密な交流が続いた。
(同時期に、東大国文科の戸石泰一、三田循司、阿川弘之、森田実蔵らも初対面している。
堤と戸石とは、程度は不詳だが知った仲にあり、何らかの情報交換があったかもしれない。)
・昭和16年(1941)12月、堤は東大を繰り上げ卒業で、徴兵検査を受け、招集も覚悟のところ、
8日に太平洋戦争が始まった。その日に太宰を訪ねたが留守で、翌日再訪し、徴兵検査結果や
戦争のこと、弟が日記をつけていることなどを話した。
(太宰の小説「正義と微笑」(S17/6)は、堤が提供したこの弟(堤康久)の日記が題材である。)
・堤は招集で4月15日(S17:24歳)に東京で入隊と決まった。
その壮行会が、4月初旬、奥多摩の御嶽1泊旅行で行われた。太宰が「正義と微笑」を脱稿した
和歌松旅館に、堤とその親しい友人の桂英澄、石沢深美、池田正憲、堤の17歳の姪、それに
太宰が加わった。堤のほかは、太宰とは初対面だった。堤が引き合わせたのである。
⁂太宰は、入隊する堤に次のように言った。
(村上護著「阿佐ヶ谷文士村」(1994:春陽堂書店)による。出典記載なく、いつの言かなど未詳)
「ちょっと、盲腸の手術で入院する位の気持ちで出かけて、そうして帰ってこいよ。決して無理し
ちゃあいけない。抜駆けの功名を立てようとしたり、卑怯未練の脱走を試みたりしてはいけない。
一切、軽味でゆくんだな。軽味、軽味だよ。これを守れば、また会える」
なお、堤は、入隊5か月、9月(S17)には学術に理解を示す軍医の計らいで除隊になった。
堤は、戦後は京都に住み、京都産業大学で教鞭をとり、同大学名誉教授。
戦後になって太宰と直接会ったのは昭和22年12月だけで、太宰に誘われて上京し、
太宰と同居して10日間(12/20~12/30)を過ごした。
堤重久の項での主な参考図書は「太宰治との七年間」(1969:筑摩書房)である。
(この作品は事実の記録というより小説(虚構)的色合いが濃いことに要注意)
ほかに「恋と革命 評伝・太宰治」(1973:講談社)、「東京新聞-在りし日の太宰治」
(土曜日:夕刊(1992/10-12)連載)、など多数ある。
(2)桂 英澄(T7(1918.6.26)~H13(2001).1.28)
・桂は、東京都出身。堤の壮行会(上記:S17/4)で太宰に初対面。堤の旧制東京府立高等学校
(現:東京都立大学)の後輩で、当時、京都帝国大学文学部哲学科の学生だったが、その後
足しげく太宰を訪ね、門弟の一人となった。
長年にわたり「桜桃忌」の世話人を務めた。
・昭和18年9月に繰り上げ卒業で、同月10日に海軍予備学生として土浦海軍航空隊に入隊する
ことになり、入隊前夜、本郷の桂宅にいつもの堤、石沢、池田が集い、そこに太宰が加わった。
⁂太宰は、桂に次のように言った。
「『軍隊に入るとね、誰も、いたわってなんかくれないんだよ。だけど、りきんだりしちゃいけない。
無理をしないで、人並みに、平凡に、ということを忘れないようにし給え』
大宰は繰り返してそう言い、軍隊生活も”軽み”の感覚で過ごせ、という言葉をはなむけとして
贈ってくれた。」(桂著「入隊前夜」より)
なお、桂は、入隊後の適性検査で館山の砲術学校に廻った。
昭和19年以来、太宰とは顔を合わせていないと書いている。
戦後、作家、文芸評論家として活動。
「早稲田文学」(S46)に発表の「寂光」は直木賞候補(S47(1972))になった。
太宰に関する文章は多数ある。「太宰治と津軽路」(1973)、「桜桃忌の三十三年」(1981)、
「わが師太宰治に捧ぐ」(2009:清流出版・・大宰追想の随筆、自作短編など収録)ほか。
桂英澄の項は、上記「わが師太宰治に捧ぐ」と「入隊前夜」(1998/6:「太宰治に
出会った日」所収)に拠った。
(3)石沢深美(T7(1918)~未詳)
・石沢は堤の壮行会(上記:S17/4)で太宰に初対面。堤の親戚で親しい友人だった。この時は慶應
義塾大学文学部独逸文学科の学生で、その後太宰を訪ねるようになり門弟の一人となった。
・卒業して、昭和18年11月1日に入隊し、一兵士として華北に送られたが、入隊の3日前に太宰を
訪ねた。いつものように、飲み屋を2-3軒回ったのち三鷹駅で別れた。
⁂太宰は、別れ際にポツリと次のように言って、かすかに笑った。
「君、戦地に行っても決して先頭に立とうなどと考えてはいけないよ。先頭から三分の二ぐらいの
所をついて行けば良いんだよ。」(石沢著「戦時下の太宰治と私」より)
なお、石沢は終戦の翌年4月(S21)に北支から復員し、その後大宰訪問を再開した。
また、NHKアジア部長、日本女子体育大学教授を歴任した。
昭和22年12月、堤重久が太宰に誘われて上京し、太宰と10日間を過ごしたが、
堤が京都へ帰る日(S22.12.30)に三鷹駅まで太宰、山崎富栄とともに見送った。
(この時の状況は、堤重久著「太宰治との七年間」の記述と大きく異なる。)
石沢深美の項は、主に本人著「戦時下の太宰治と私」(「太宰治研究3」
(H8:和泉書院)所収)に拠った。
(4)池田正憲(生没年未詳)
・池田は堤の壮行会(上記:S17/4)で太宰に初対面。堤の府立高等学校の後輩で、当時、東京
帝国大学文学部仏蘭西文学科の学生だった。那珂太郎らと辰野隆教授の試験を受けている。
〈那珂の戦中日記(S18.9.3))。
・大宰と初対面後の交流に関する資料は見当たらなかったが、那珂太郎の戦中日記の9月3日
(S18)には次のようにある。
「池田は太宰さんをほんとうに尊敬してゐる。池田の太宰さんの話をきいているうちに、
何だか太宰さんに逢ひたくてたまらなくなってきた。」
那珂は、9月2日の夜に池田と歓談してこの気持になり、翌3日に大宰を訪問したのである。
その様子は既述(Ⅰ-2-(2)-①)の通りだが、3年半ぶりの太宰再訪の陰には池田がいた。
なお、池田は、「現代詩手帖-那珂太郎 戦中日記:注記」」に、「後に俳句作家。」とある。
2.戸石泰一 (T8(1919.1.28)~S53(1978).10.31)
(1)太宰治にのめり込む・・初対面
・戸石は仙台市で生まれ、旧制仙台一中、旧制二高文科を経て昭和15年(1940)4月、東京帝国
大学文学部国文科に入学、東京で下宿生活となった。
・高校時代に太宰の作品に感動して読み耽り、東大入学の年の12月13日、東大の1学年先輩で
同人誌「芥」(*)仲間の三田循司と三鷹の太宰宅を訪ねて初対面した。一人では心細いので、
最も敬愛する友人で詩人を志す三田を誘った。(三田については次項に詳記)
(*)同人誌「芥」は、二高、仙台一中出身の戸石の同級生を中心に創刊(S15/3)。
同人は戸石、三田循司、森田実蔵ら11名で発刊、第3号(S16/3)で終刊。
なお、森田や三田の弟は、戸石、三田は二高時代にも「芥」を発行したという。
・以降、二人は太宰に師事し頻繁に太宰を訪ねた。時に同級の阿川弘之や森田実蔵らを誘うこと
もあったが、特に戸石は大宰との親密さを増し、大学二年になると(S16)三鷹に少しでも近づき
たいと荻窪の知人宅に下宿させてもらった。
(前記の通り、同時期に東大独文科の堤重久も大宰を訪ねて初対面している。
戸石と堤とは、程度は不詳だが識った仲にあり、何らかの情報交換があったかもしれない。)
(2)太宰治著「未帰還の友に」のモデル
①繰り上げ卒業、仙台で入隊
・大学二年生時(S16)に繰り上げ卒業が発表され、三年生は12月、二年生は翌年(S17)9月の
卒業と決まった。徴兵検査を受け、多くは卒業すると直ぐに入隊だった。
(三田は、この12月に卒業し、翌年(S17)2月、盛岡で入隊した。)
・戸石は、翌年9月(S17)に卒業、10月1日に仙台で入隊した。
卒業直前、何回か大宰を訪ねて飲んだ。卒業式前夜(S17.9.24)には同級の阿川弘之(9月に
海軍予備学生で入隊)ら友人たちと別れの会を開き、太宰、山岸外史にも来てもらった。
賑やかに飲み笑い、心残りないという思いで別れた。
・大宰の「10月9日付ハガキ」がある。「拝復」とあり、入隊直後の戸石への返信である。
そこには、堤が遊びに来たこと、軍服のサイズのこと、タマに死すとも病いに死ぬな、などとあり、
戸石は「できれば堤のように帰れればいいな」と慰められるような内容だったという。
②南方へ赴く途中、上野で太宰に会う。
・戸石は陸軍予備士官学校へ進み、翌年(S18/12)卒業、見習士官となって南方へ赴くことに
なった。仙台を発ち(S19.1.7夜)、大阪で乗船するので、上野で乗り換えのため約6時間の
自由時間があった。(*)
・戸石は、太宰に上野駅で会いたいと電報を打った。
上野駅には朝5時半前に着く予定のところ3時間くらい延着となった。太宰は三鷹の飲み屋を
手配して早朝から待ったが、時間が無くなり、止むを得ず上野公園内の茶店で歓談して別れた。
(*)「太宰治の年譜」(山内祥史著)によれば、
・戸石の任地は、南方軍総司令部だった。
大阪港を貨物船朝日丸で出航。スマトラの第25司令部付少尉だった。
・戸石と太宰が上野で会った日は7日夜仙台発であれば8日だが、「1月9日」とある。
(出典は戸石の著作「青春」(S31:「太宰治研究」(筑摩書房)所収)
③終戦-「未帰還の友に」(太宰)-再会
・戸石は南方の島で終戦を迎え、昭和21年7月に復員、仙台に帰った。
直ぐに、入隊中に太宰が発表した作品を読んだ。中に「未帰還の友に」(S21/5)があった。
小説は、戸石が大宰と上野で会った時のことから始まっており、戸石は「未帰還の友」の「友」
は自分であると確信し、太宰はこんな思いで自分を待っていてくれたのだと思うと直ぐにも会い
たくなって太宰の疎開先へ手紙を出した。
・しかし、諸状況から会えないまま時間が過ぎ、再会はその年の11月になった。
その日(S21.11.13)、戸石が河北新報社(*)に出勤すると、机上に太宰が訪ねてきたというメモ
があった。駅へ行くと、疎開を終わり帰京途中の太宰が家族と共に仙台で下車していた。
(*)戸石は復員して10月に河北新報社に入社した。
太宰は、同社に「惜別」(S20/9)の資料で世話になり、
「パンドラの匣」を連載(S20/10-1)するなど関係が深い。
・上野で会ってからほぼ3年ぶりの再会だった。
太宰は家族を仙台ホテルで休ませ、戸石、宮崎泰二郎(河北新報社幹部)らと酒になった。
太宰一家は仙台に1泊。翌14日、太宰は家族に仙台の街を見せた後、戸石夫妻が見送って
午前10時発の急行に乗り帰京した。
④その後・・
・年が明けて昭和22年(1947)、戸石は上京すると太宰を訪ねて酒になった。
しかし、徐々に太宰不在、連絡が取れないことが増えていった。
大宰と「ヴィヨンの妻」のことや「斜陽」執筆のことを話した以降については、戸石には具体的な
記述が見られないので、最後に会ったのは、この年(S22)の春頃だろう。
・太宰は、疎開から三鷹に戻ってからは、超多忙の日が続き、複雑な女性関係なども加わって、
以前の生活環境、交友関係は一変していた。
戸石は生活に追われる状態が続いており、大宰との関係に一層の寂しさを感じていたようだ。
そして翌年、太宰は山崎富栄と玉川上水で入水心中(S23.6.13)した。
戸石泰一の項は、主に本人著「青い波がくずれる」(S47/12:東邦出版社)に拠った。
本書は「青い波がくずれる-田中英光について」、「そのころ-小山清とのこと」
「別離-わたしの太宰治」の三作から成る。事実に沿った内容と見てよかろう。
3.三田循司 (T6(1917.9.17)~S18(1943).5.29)
(1)太宰治に初対面
・三田は岩手県花巻市で生まれ、旧制岩手中学校(私立)、旧制二高を経て昭和14年(1939)
4月、東京帝国大学文学部国文科に入学、東京で下宿生活となった。
・詩人を志し、前記した同人誌「芥」に詩を発表するなど、同窓、同人仲間で1学年後輩の戸石泰一
と親しく接し、その誘いで昭和15年12月13日、二人で三鷹の太宰を訪ねて初対面した。
・三田は、この日の日記(*)に次のように書き、感動を示している。
「実によかった 胸襟を開いて、気取らず尊大ぶらず、我々青年学生と同じ気障で(?)我々の
(Generationの)考へ(今後の文学、考へ方、感じ方、表現etc)に相似た、多少我々よりおくれて
ゐる様な気はしたが。最も感銘の深かった言―作品の深さは、作家がその作品において失ったものの
深さにある。古典を素直によみ直して糧を得る。自己の要求のまゝに本etcをあさること、等。(探求)」
・以降、二人は頻繁に太宰を訪ねたり手紙を書いたりしたが、三田は下宿近くに住む山岸外史も
訪ねていた。戸石によれば、太宰を介して知ったとのことだが、三田の昭和15年5月27日の日記
に「山岸外史氏は云ふ 「人生耽美」」とあり、この時すでに会っていたかもしれない。
戸石は太宰に夢中で親密さを増したが、三田は山岸への傾斜を強めていった。
(*)三田は18冊の日記を遺している。1冊目は昭和11年(1936)5月(二高時代)から
始まり、18冊目は昭和16年12月8日までである。(この12月8日は太平洋戦争開戦
の日であり、この日に三田は徴兵検査を受けた。)
このうち、13冊目(S15./5..3-.30)から18冊目まで、慶應義塾志木高等学校の
小澤純は部分翻刻し発表している。(下記の参考資料参照)
(2)山岸外史に傾斜
・翌年の三田の日記には、「太宰さんの文章-又かといやになることがある」(S16.10.16)とか
「山岸さん-血-(温い)-(心臓の) 太宰さん-水-(冷たい)(流れの)」(S16.11.26)
という記述があり、他にも山岸の著作や言動に関する記述が多くなっている。
大宰への畏敬の念は変わらないが、山岸への傾斜の様子が窺える。
(3)繰り上げ卒業-入隊-アッツ島で戦死
・三田は、3か月繰り上げで昭和16年12月卒業となり、卒業後は、4月から東京国立の中学校に
勤めることになった。3月までは郷里の花巻で過ごすことにして12月27日に帰郷した。
山岸宛の帰郷挨拶ハガキ(S16.12.28付)に、国立の帰途、三鷹へ寄ったとあり、「何といふ
さびしさうな、すがれた姿だったでせう。」と記している。太宰に会った印象だろう。
・ところが、翌1月(S17)、召集令状が届き、2月1日に盛岡で入隊した。
太宰に召集を知らせたところ、太宰から次の返信(S17.1.26消印ハガキ)があった。
「拝復、けさほどは、おハガキを いただきました。召集令がまゐりましたさうで、
生きる道が一すぢ クッキリ印されて、あざやかな気が致しました。おからだ
お大事になさって、しっかりやって下さい。はるかに 御武運の長久を祈る。不一。」
・三田が転属した部隊はアッツ島守備を任務として島に渡った。
アッツ島は、5月(S18)に米軍の激しい攻撃を受け、12日から29日までの戦闘で守備隊員
約2,500名は、ごくわずかな生存者のほかは全員が戦死した。
「アッツ島玉砕」として8月29日の朝日新聞に戦死者名が掲載され、「三田循司」の名もあった。
(4)太宰治著「散華」のモデル
・太宰に「散華」(S19/3)という短編小説がある。二人の若者の死が描かれ、一人は「三井君」で、
創作した人物だが、もう一人は三田循司で、実名で登場し、戸石泰一も「戸石君」で登場する。
両者の交友や太宰、山岸との関係、出来事などはほぼ事実に沿って書かれている。
・太宰は兵隊となった三田からの便り、最後の一通に感動した。この便りは「最高の詩」と評し、
作中で3回にわたり引用している。太宰はこの便りをもって、それまであまり高く評価しなかった
三田を「いちばんいい詩人」と認め、早くから高く評価していた山岸に承服を伝えた。
・太宰は三田のこれからの詩業に大いに期待したが、戦死を知って、「三田君の作品は、全く別の
形で立派に完成せられた。アッツ島における玉砕である。」と書いた。
太宰は、山岸が遺稿集(*)を出版するというので、この最後の便りをその開巻第一頁に大活字で
載せてほしいと思ったとして、この便りの三度目の引用で「散華」を結んだ。
(*)河北新報(S56.8.13付))によれば、山岸は、太宰が「散華」を発表した直後に
三田を主人公にした250枚の「北極星」をまとめたが、発禁となった。
また、山岸が準備を進めた遺稿集は発行に至らなかった。
・「散華」は、太宰と三田との実際の関係が軸になっているが、作品はあくまでも創作である。
戸石、森田実蔵によれば、作品の核心である三田の最後の便りにも太宰の手が入っている。
・「散華」にある最後の便りは次の通り。( / は改行)
「御元気ですか。 / 遠い空から御伺いします。 / 無事、任地に着きました。 /
大いなる文学のために、 / 死んで下さい。 /
自分も死にます、 / この戦争のために。」
・戦後、戸石が三田を主人公に書いた「玉砕」(S27/9:「小説朝日」)では次の通り。
「先生 / 死ンデ下サイ / 文学ノタメニ /
私モ / 死ニマス / 大イナル戦争ノタメニ」
森田は、「戸石が太宰家から、その葉書を借覧したということを勘案して、
多分これが原文だろう。」としている。(「太宰さんの思い出」(H8/7))
・小澤純によれば、これに関する三田循司の弟(三田悊)のメモがあり(日本現代詩歌文学館所蔵の
「資料番号93609」)、そこに、悊(せい)が記憶している文面が次の通り書き残されている。
「お元気ですか / 遠い空から おうかがい いたします / 大いなる 文学のために死んで下さい /
私も死にます / この戦争のために」
小澤は、各文面が書かれた当時の状況を考慮すると戸石が自作の内容に沿って原文を変更した可能性
もあるとしたうえで、それぞれの「大いなる」という美辞の宛先をめぐって考察を進めている。
・太宰は三田の戦死を知った。感動したこの便りは「生涯最後の便り」となってしまった。
「散華」は、表題を「玉砕」ではなく「散華」にしたこと、三井君の美しい死(肺結核)を
描いたことで、三田の心をしっかりと受け止めた太宰の小説とし、アッツ島の空に思いを
馳せた「鎮魂の書」になっている。
なお、太宰の太平洋戦争中の多くの作品には戦争に対する「芸術的抵抗」が
見られると評し、「散華」もそうした作品の一つとの見方がある。
これら「散華」に関する詳細は次の別記項目を参照ください。
「太宰治「散華」-三田循司君はアッツ島で戦死」(2023/6UP)
(三田循司の項の主要参考資料)
・戸石泰一著「青い波がくずれる」(S47/12:東邦出版社)
同 「玉砕」(1952/9:小説朝日)・・「展」(創刊号・1980/12:明窓社)に転載)
・慶應義塾志木高等学校「研究紀要 第52輯」(2022/5)、「 同 第53輯」(2023/4)所収
・小澤純著「三田循司関連資料」(日本現代詩歌文学館所蔵)調査報告書」
―太宰治「散華」と、三田循司日記の部分翻刻(稿)を中心にー
・同 著「太宰治「散華」/「三田循司関連資料」の教材化と三年東北見学旅行」
・森田実蔵著「太宰さんの思い出」(H8/7:和泉書院「太宰治研究3」所収)
・ネット(HP)=石櫻同窓会(三田循司出身の私立岩手中学の同窓会)
(「石桜同窓会」で検索、「温故知新」の項があり、その中に「三田と太宰との
関連」など詳細な記述がある。大宰からの葉書の実物写真や関連新聞記事、
山内祥史著「三田循司と太宰治」(「太宰治研究18」所収)など資料類も多い。)
・山内祥史著「太宰治の年譜」(2012:大修館書店)
・・おわりに・・
①那珂と三田の戦中日記
・那珂の日記には近々入隊必然の自分と、同じ立場の仲間や師とした太宰、山岸との交流、
自身の生き方への迷いなどが率直に書かれている。
・発見者の小澤純は、特に太宰との関連で「こうした戦時下のやりとりの細部が、太宰没後の
回顧というフィルターを通さないまま日記ノートに保存されていたことの貴重さ」を強調して
いるがその通りだろう。
・三田の日記もまた同様である。那珂の場合には、このノートが他人の目に触れることを意識
していることが窺えるとはいえ、両日記とも、応召、戦死を覚悟せざるを得ない状況にあって、
冷静に生き方を思い、書き留めている。まさに真情の迫力がある。
・ただ、戦争そのものへの見識は書かれず、戦争を抵抗なく受け入れているところは気になる。
兵士となって戦うのは国民の務め、戦死は覚悟のうえという前提で生きるしかなかったという
ことだろう。
天皇を頂点とする体制に組み込まれた大部分の日本人の共通認識だったことが窺える。
②太宰は「軽み」を説く
・入隊を前にした文学青年に太宰が説いたのは「軽み」だった。
要は人並みに、平凡に、普通に振舞って「生きて帰ってくれ」ということだろう。
息子の出征を見送る親の本音と同じといえよう。
・太宰の戦争観に関しては、研究者らが多角的に多くの論考を発表している。
私見になるが、太宰は平和、平穏を心底から願いながらも、戦争に対しては、始めたからには勝た
ねばならないと現実を受け入れており、この意味で天皇を頂点とする体制に組み込まれた大部分の
国民と同様の認識だったと言える。
ただ、太宰は、この状況の中でも悔いなく生きよう、自分は文学に生きる、その道しかなく、
文学で成功するという強い意志を持ち、それを表明している。
・このことは、特に太平洋戦争開戦時の三作品「新郎」(S17/1)、「十二月八日」(S17/2)、
「待つ」(S17/6)にはっきり表れている。「散華」もそうだが、厳しい検閲下、相対化など
筋立ての工夫、太宰独特の皮肉たっぷりの道化、大袈裟な表現などで行間に真意を込めている。
「芸術的抵抗」と評される所以だろう。
(詳細は別記「新郎」および「十二月八日」を参照ください。)
③戦後の人生
・本項の文学青年たちは、三田の他は全員が復員し、それぞれの新たな人生を歩み始めた。
軍隊生活は各人各様だったが、那珂は、海軍予備学生として入隊、一般兵科に配属され、
海軍兵学校の教官になって終戦を迎えた。飛行科に配属の同期生の過半は戦死した。
「個人の意志を越えた「偶然」と言ふしかない選別によって、人の運命が決められたことに、
やり切れない思ひがする。」と書き、さらに、「のちのちまで、戦死した同世代者に対して償い
やうのない負目をおぼえざるを得なくなった。」と書いている。(那珂太郎ーはかた随筆集)
早々に除隊となった堤や徴用を免れた太宰も同様の思いを抱いている。
戦後、平和を享受することができた多くの国民に共通する思い、後ろめたさでもあろう。
・太宰の交友関係は一変した。堤、戸石らは戦後再会したことを書いているが、会ったのは1回
ないし数えるほどの頻度で、師弟というより大先輩と後輩のお付き合い程度の感がある。
それも昭和22年(1947)までで、翌23年(1948)には会っていないだろう。
各人が新時代にあって自分の道を拓くのに精一杯だったことと太宰の変化が背景にある。
疎開から帰った(S21/11)太宰は執筆に追われ、「斜陽」(S22)で大流行作家になるが、
一方で家庭や女性、金銭問題、飲酒や健康面などで実生活は大きく乱れた。
交友関係は、井伏鱒二が、太宰は「旧知のわずらわしさ」を感じていると表現した状態だった。
・太宰は玉川上水で入水心中(S23.6.13)し、翌年から、友人らが大宰を偲ぶ桜桃忌(6月19日)を
開催するようになった。
桂英澄はその世話役を長年続け、堤、戸石は出席の常連メンバーだった。
(詳細は、次の別記項目を参照ください。) |
------------------------------------------------
=那珂太郎 略年譜=
・T11(1922)1.23. 福岡市麹屋町(現博多区)で呉服商酒井家の五男として出生。
正次郎と命名。生後半年ほどで同業の福田家の養子となる。
・9歳の時(S6・1931)市内で転居、その家の裏は那珂川に面し、沈む太陽と川面と
雲が彩なす風景に切ない感覚、自身の存在に恐怖を覚えるような感性だった。
・福岡中学校、福岡高等学校文科乙類(*1)に進み(S13)、同人誌「こおろ」(*2)
に参加、第3号(S15/7)に福田正で「界」が載ったが発禁となり雑誌は没収された。
同人の中心者は先輩の矢山哲治で、真鍋呉夫、島尾敏夫、阿川弘之らの先輩や、
乙類同級生の猪城博之、甲類の千々和久彌、丙類の小島直記らが同人で作品
投稿や文学論議を戦わせた。
乙類同級生の伊達得夫 湯川達典は「こおろ」に参加しなかったが、那珂とは特に
親密で「こおろ」同人らとも親交が深かった。
・クラス雑誌「青々」(*3)やクラス回覧雑誌「止里可比」(*4)に詩や小説を掲載した。
(「こおろ」(誌名は第4号から「こをろ」)、「青々」掲載の著者名は福田正次郎や
福田正だが、「止里可比」(第1巻4号:S19/9)に掲載の詩は「那珂太郎」名。
(*1)乙類は履修する第一外国語が独語。甲類は英語、丙類は仏語。
(*2)創刊号(S14/10)~第14号(S19/4)を発行、第4号(S15/9)から「こをろ」。
誌名は、「古事記」国産みの段「塩こをろこをろに攪きなして」から採った。
(「第3号」の発禁は、真鍋呉夫「野良犬物語」が時局に背くという理由)
(*3)「青々」は、S15/1創刊~S21/10(5号)発行の同校文科乙類クラス雑誌。
旧制福岡高校は「青陵」と称されており、これに因んだ誌名だろう。
(*4)「止里可比」は、同校出身者が発行したクラス回覧雑誌で、S17~S19に7冊を
発行、2冊のみが現存。学校所在地「鳥飼=とりかい」に因む。寄稿者の一人、
田中小実昌の随筆「回覧雑誌「止里可比」のこと」(2016:「題名はいらない」
所収)に、「鳥飼の古語で、万葉集にもでているとかきいた。」とある。
・S16(1941)/4(19歳) 東京帝国大学文学部国文科に入学。
・S18(1943)/9(21歳) 東京帝国大学を繰り上げ卒業。
・ 同 /10(21歳) 海軍予備学生として土浦海軍航空隊(一般兵科)に入隊。
・ 同 /12(21歳) 広島県江田島の海軍兵学校 国語科教官となった。
・S19(1944)/5(22歳) 海軍少尉に任官。以降、海軍兵学校教官として分校に転属
(S20/4:長崎県針尾、S20/7:移転で山口県防府)。
・S20(1945).8.15(23歳) 終戦時は海軍中尉(S20/6)。翌9月、郷里福岡市に復員。
・S20(1945)/10(23歳) 上京して、私立東洋高等女学校国語科時間講師など。
・S21(1946)/3(24歳) 都立第十高等女学校(現豊島高校)教諭。(詩作を続ける)
・S25(1950)/5(28歳) 第一詩集「ETUDES」(S25)を、本名「福田正次郎」で刊行。
・S26(1951)/5(29歳) 「歴程」同人。
・ 同 /5(29歳) 教え子と結婚。(一男二女を授かる)
・ 同 /9(29歳) 都立新宿高校(定時制)に異動。(以降21年半勤務)
・S36(1961)/12(39歳) 杉並区久我山に新居、移転。(のちに「空我山房」と称す)
・S48(1973)/4(51歳) 玉川大学助教授(翌年(S49)教授)となり文学活動を続ける。
・作品の受賞
詩集「音楽」(思潮社:S40・1965)=室生犀星詩人賞・読売文学賞
詩集「空我山房日乗其他」(青土社:S60・1985)=芸術選奨文部大臣賞
詩集「幽明過客抄」(思潮社:H2・1990)=現代詩人賞
詩集「鎮魂歌」(思潮社:H7・1995)=藤村記念歴程賞
・日本芸術院賞・恩賜賞受賞(H6/6・1994)
・勲三等瑞宝章受章(H7秋・1995)
・H26(2014).6.1.(92歳) 死去
(本略年譜は、主に「那珂太郎―はかた随筆集」(2015/11:福岡文学館発行)に拠る)
|
-----------------------------------------------------------------------------
(本項「太宰治と新発見の「那珂太郎 戦中日記」をめぐって」 R5(2023)/4UP)
|